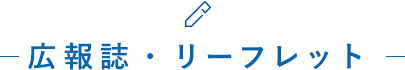院長室から
父母の帰郷
〜ヒューマニズム溢れるエッセー集
患者との温かい関わり、生い立ちや父母への思いなどを院長自らが綴ったヒューマニズム溢れるエッセー集
「北海道で眠りたい。父さんの骨を北海道へ連れていってくれ。」
飛行機の窓の下に広がる蒼い津軽海峡を見ながら、死が目前に迫った父の三年前の言葉を思い出していた。
平成六年一月、肺癌を告知され、回復に全力を傾けていた父も初夏には肝臓への転移を知り死を覚悟するようになった。母の死後、両親のいる鹿児島に戻ることを選択した父だったが、十年目の夏、帰らぬ人になった。
祖父が眠る墓の墓石を石屋さんに前方にずらしてもらい、階段を降りた。光がほとんど入らない空間の中で骨壺を捜すのは想像していた以上に困難であった。父の骨壺はすぐわかったが、母の骨壺を捜すのに手間取った。見覚えのある薄緑色の骨壺をようやく、こころもとない懐中電灯の下で見つけた。十二年前に墓石の下に置いたまぎれもない母の骨壺であった。
ご住職にお経をあげていただき、祖母、弟と私の三人でお参りをした。父の遺言通り北海道に墓を建てることに同意してくれた祖母であったが、「子供の所に行くんだから幸せだね」と、頬から涙の雫を流しながら、自分自身に言い聞かせるように咳いた言葉が心に沁みた。
飛行機が新千歳空港に着陸した。両親の骨壷を持って北海道の土を踏めたという実感を噛みしめながら、「綾ちゃんが戻ってきたら教えてね」と、毎年元旦に電話をいただく母の友人に、母の帰郷を知らせようと思った。